
 あや
あやこのような 疑問はありませんか?
子供のやる気を引き出したい
やる気スイッチを押す声かけも知りたい!
この記事では、子供のやる気を引き出すポイントと子どものやる気を引き出す親の役割を紹介します。



子どもをやる気にするために実践したことをお伝えします。
- 子供のやる気を引き出すポイント6つ
- 子どものやる気を引き出す親の役割
- やる気を引き出す声掛けのデータ
記事後半では、子供のやる気を引き出すためにどのような声かけが良いのかをお伝えします。
お子さんのやる気を引き出すヒントになります。ぜひ参考にしてください。
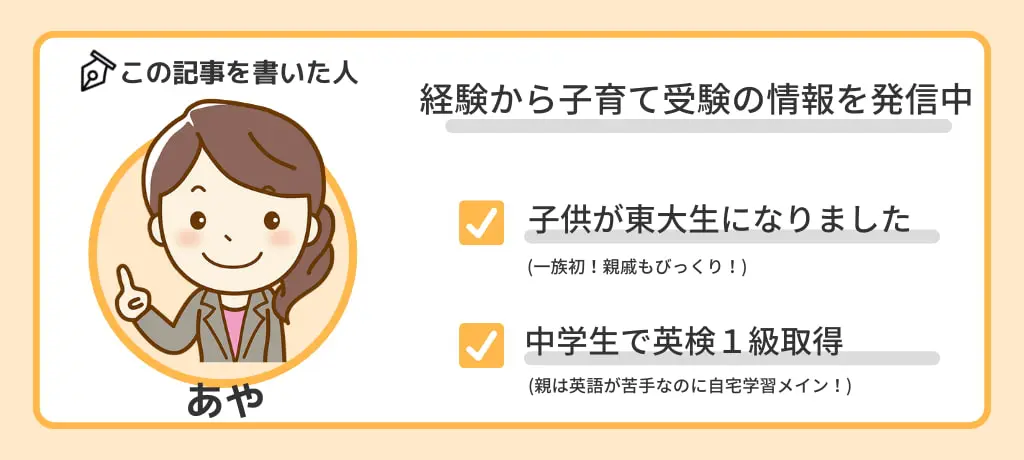
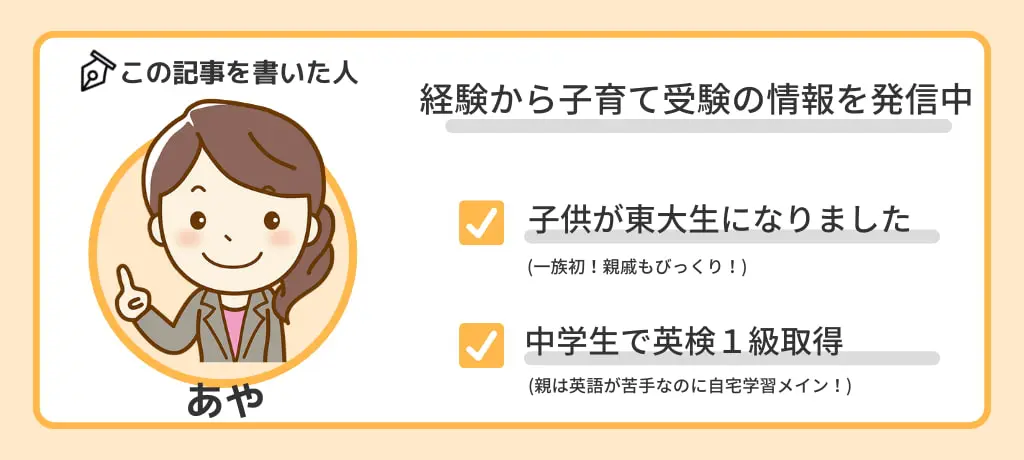
子供のやる気を引き出すポイント





こどものやる気を引き出す方法を解説します。
- 小さな成功体験を積み重ねる
- やる気になる環境をつくる
- 習慣化でやる気を引き出す
- 難しい勉強ばかりさせない
- 勉強をやらせすぎない
- 目標を決めて勉強をする
➊小さな成功体験を積み重ねる


子どもの成功体験は、何かで優勝するとか大きな物である必要はありません。
例えば小学校の小テストで100点を取るといった小さなことで十分です。小さな成功体験の積み重ねで、子どもは普段の努力の成果を実感し、やる気が引き出されます。
何よりも、同級生から「勉強の出来る子」と認定されるようになると、自己肯定感が高まり、勉強へのモチベーションが上がります。
学校での成績をキープすると、やる気がアップし、持続させるポジティブな「スパイラル効果」が生まれます。



なつきの場合
3年生の理科のテストで学年で1人だけ100点を取りました。
小さな成功体験が勉強へのやる気を引き出すきっかけとなりました。
❷やる気になる環境をつくる


やる気を引き出すには、集中して勉強できる環境を整えることが大切です。
例えば、学校から帰ってきた時に誰かがゲームをやっていたり、テレビを見ていたりすると、勉強する気持ちがなくなってしまいます。
また、リビングや子ども部屋が汚れていて、ゲーム機やマンガ本が置きぱなしになっていてもやる気がでません。
特に低学年のうちは、毎日の生活の中で、いつ勉強するのかを決め、時間になったら親が勉強する雰囲気作りをし、誘導して環境を整えてください。
環境を整える具体的な方法
- 教材を事前に用意する
- 勉強スペースを整えておく
- 飲み物を用意する
- 集中力を妨げるスマートフォンをミュートにする



子どもは学習に集中し、効率良く勉強を終わらせることができます。
❸習慣化でやる気を引き出す


ご飯の時間が決まっているように、勉強も決まった時間に行い、習慣化するのがおすすめです。
例えば「学校から帰ってきたら宿題をしてから遊ぶ」「1日にやる勉強時間が終わったら自由時間にする」など、毎日のスケージュールを計画的に立てましょう。
勉強する時間が決まると、自然に気持ちの切り替えができるようになり、習慣化とつながります。
おすすめの勉強タイム
- 朝ご飯から登校前の時間
- 学校の帰宅後から夕方までの間
- 夕食後の時間帯



我が家では入園前から中学生(3年生)まで、登校前の勉強を徹底しました。
❹難しい勉強ばかりさせない
子どもが学ぶ意欲を持ち続けるには、難しい勉強ばかりさせるのではなく、達成感を感じられる内容も取り入れることが大切です。
例えば、得意な教科や興味のあるテーマを勉強する時間を設けると、モチベーションを維持できます。



小学1年生の時にパソコンのタッチタイピング を覚えたよ。
❺勉強をやらせすぎない


長時間の勉強は子どもにとって負担となり、逆にやる気を失わせてしまいます。適度な休憩や遊びの時間を取り入れ、バランスの良い生活を送ることが重要です。
1日の勉強時間を設定し、無理のない範囲で勉強を継続することを心がけましょう。
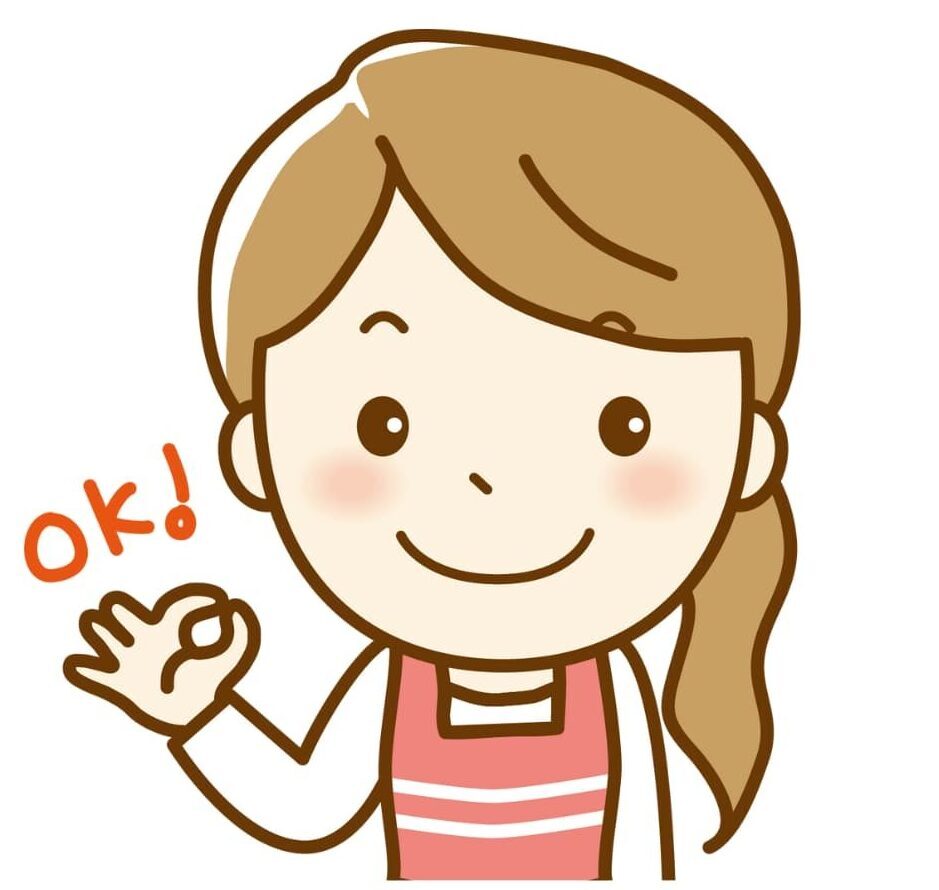
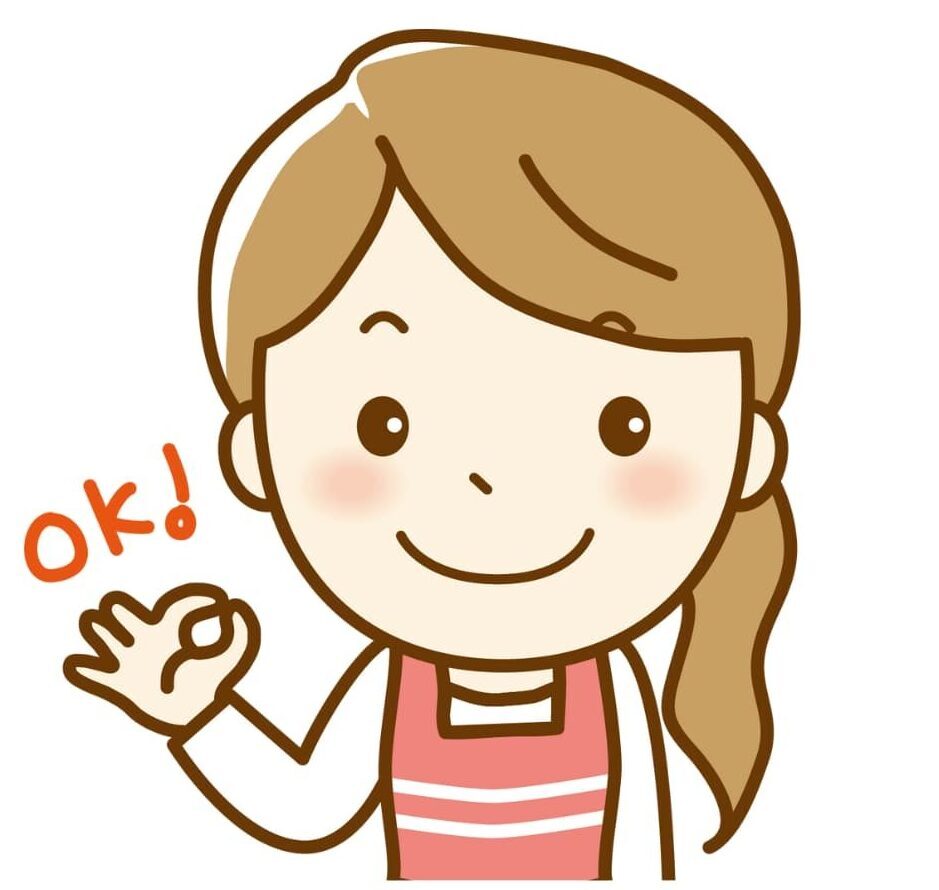
< POINT>
今日の目標の学習が終わったら終了し、達成感やもう少しやりたいかなと思わせるのも大切。
大人も仕事や家事が終わって、追加されたら嫌ですよね。
あやのここだけの話
私立小学校に通っていました。
熱心な保護者の方が多かったので、過度にやらせているなぁ~と感じたことを紹介します。
➊ ストーリー


○○君の音読カード。
間違って持って来ちゃった💦
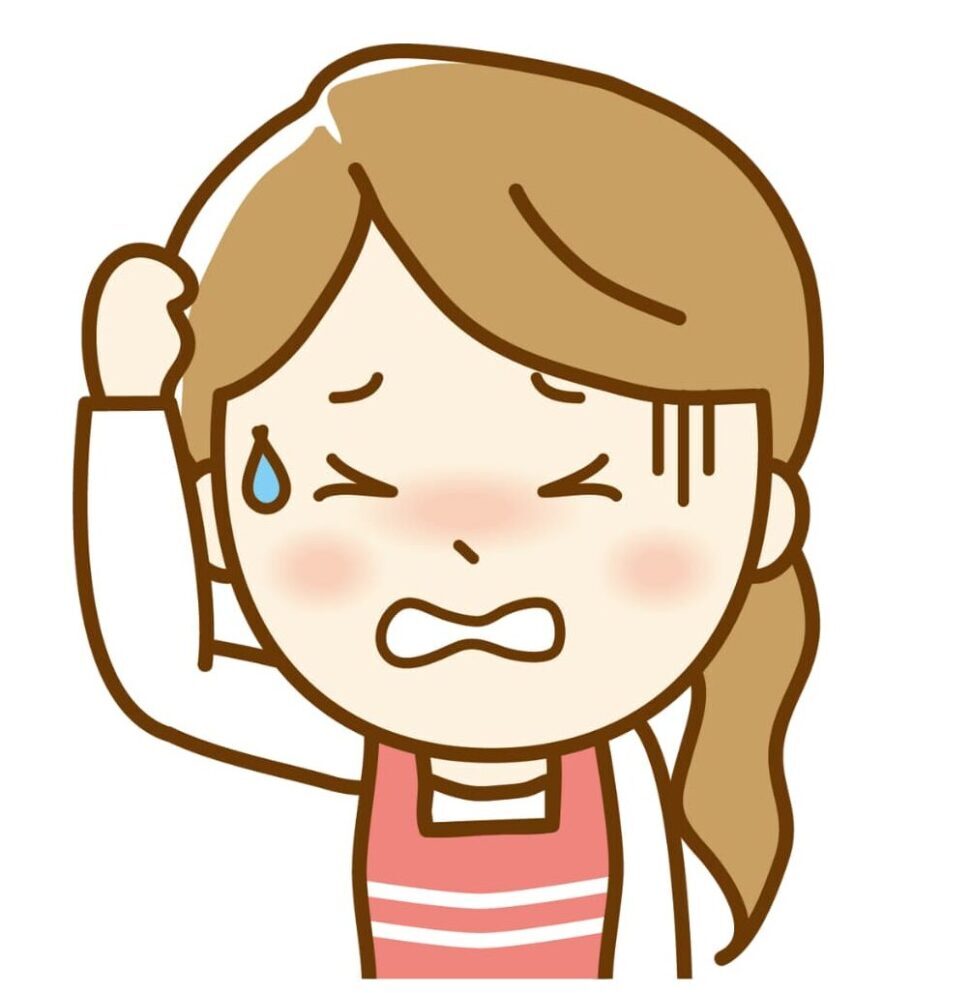
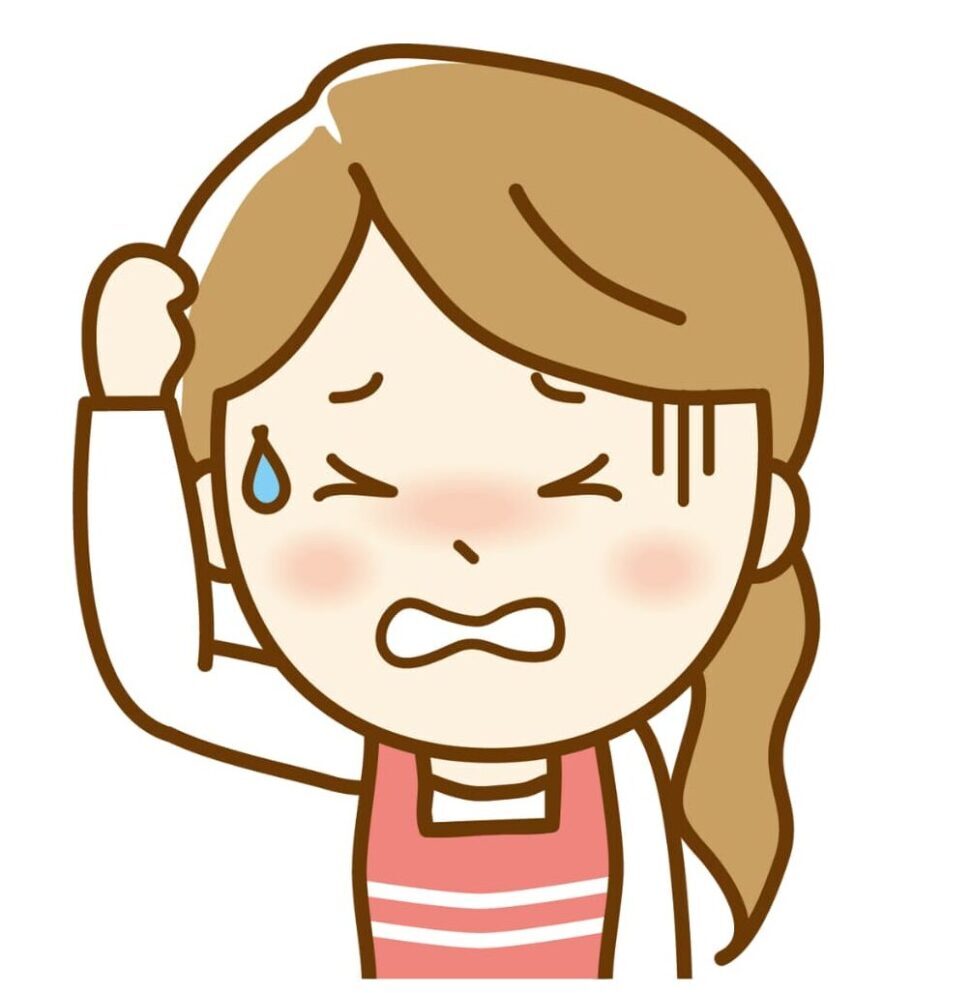
どれどれ、見せてね。
その回数を見て、驚愕👀
1日に30回以上も読んでいた💦
❷ ストーリー


○○君のお家にコピー機があるから、KUMON(くもん)のプリントコピーしているんだって。
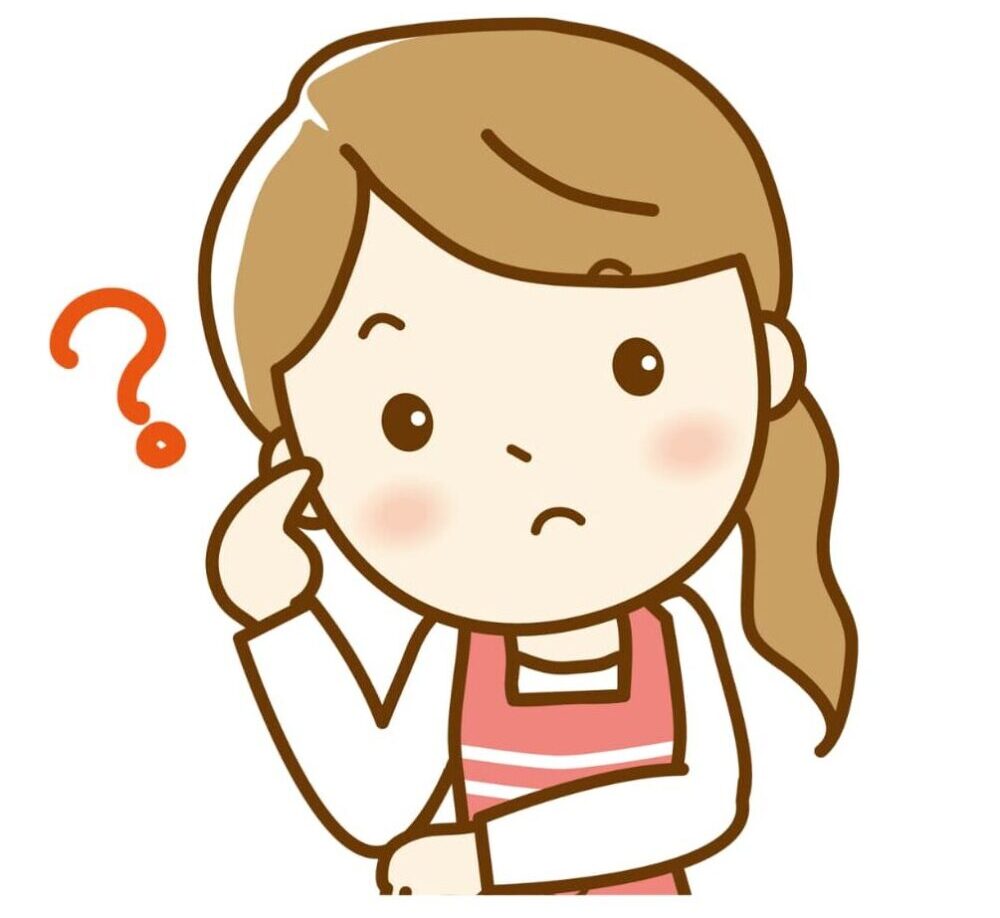
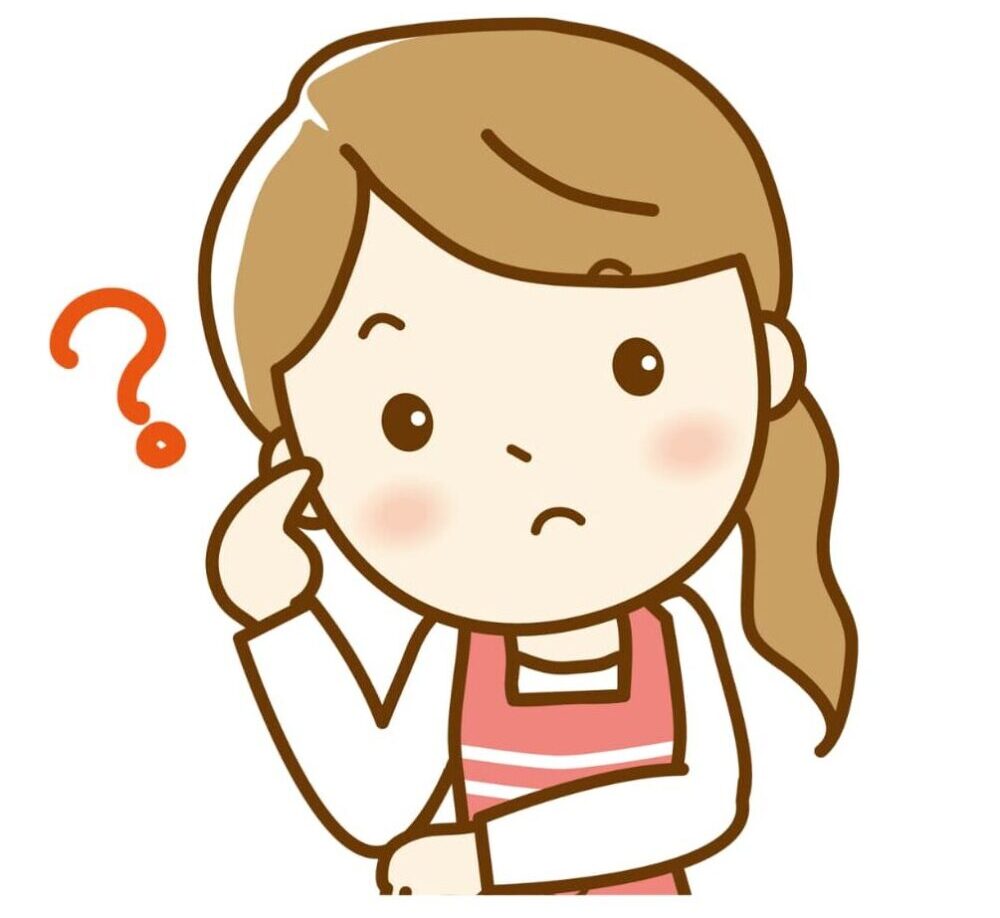
凄いね~
毎日どの位やっているのか、聞いた?


毎日100枚、やっているって!
もう何千枚も、やったって言っていたよ。
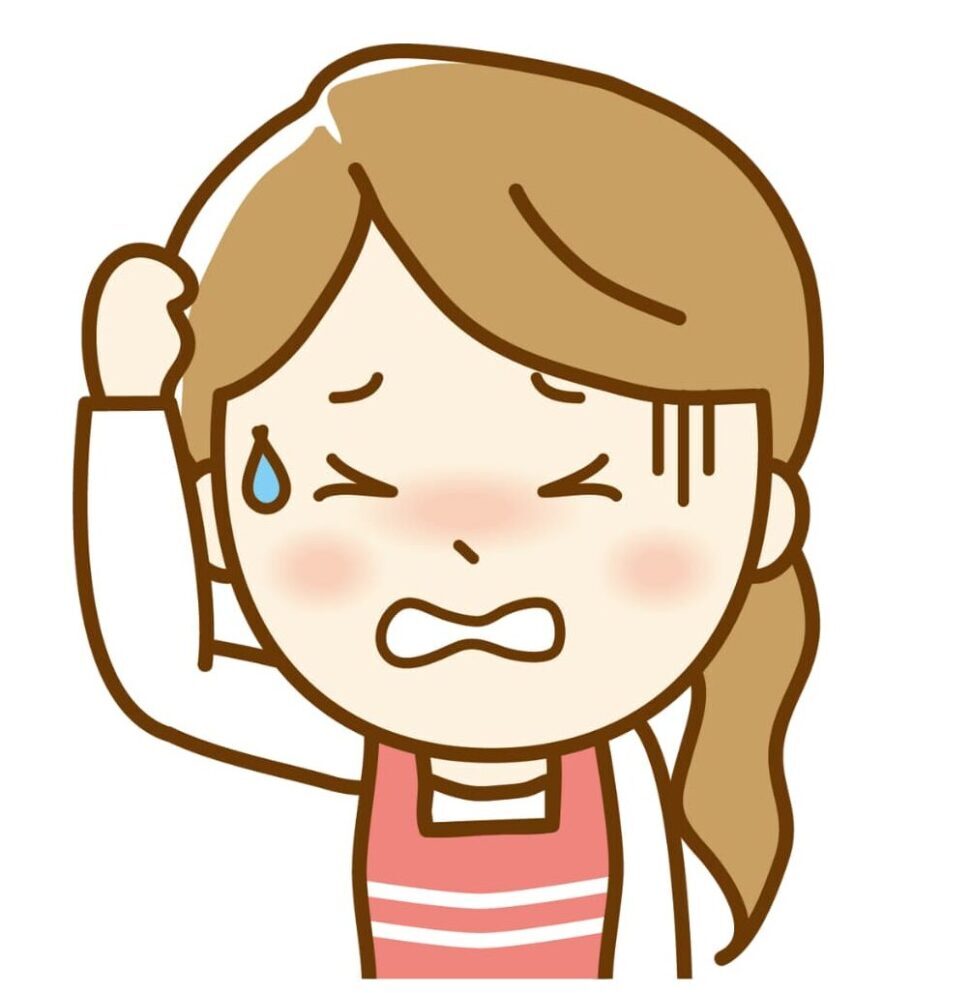
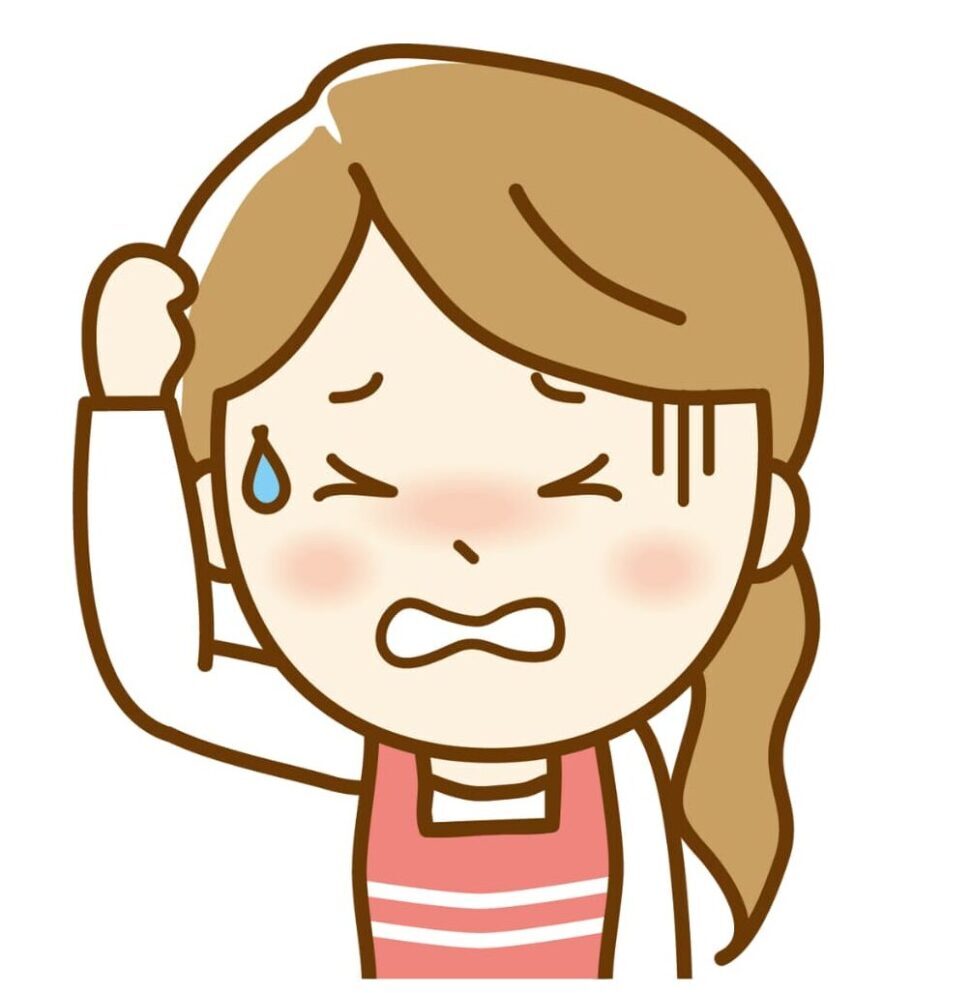
何、何千枚!
みんな、そ・そんなに頑張っているんだね💦
単純な作業を大量に繰り返すより、新しいことに挑戦したり、子供の興味のある分野に取り組むのがオススメ!
❻目標を決めて勉強をする


勉強に対してやる気を引き出し、効果的に学習を進めるには、具体的な目標を設定することが重要です。
目標を持てば、自分がどの方向に向かって努力しているかが明確になり、達成感やモチベーションアップにつながります。
目標を持って勉強すれば、自分の成長を実感する大きな原動力となりますね。
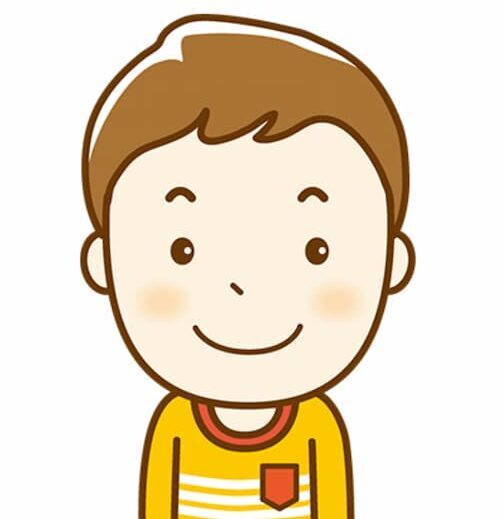
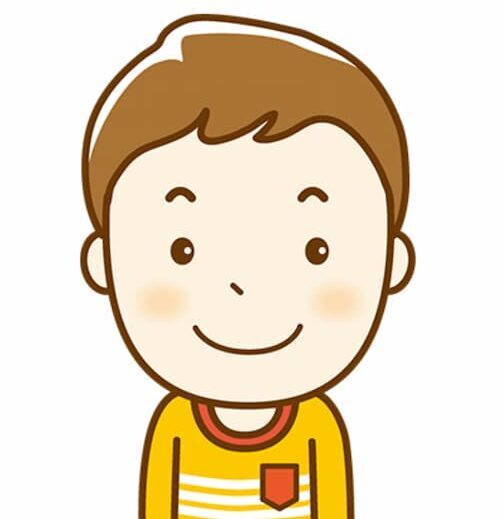
スモールステップを繰り返して、計画的に学習を進めましょう。
子どものやる気を引き出す親の役割


①親が一貫性を持つこと
親が一貫性を持って子どもに接すると、子どもは安心感を持ち、ルールや期待に応えようと意欲が高まります。
例えば、勉強時間やルールを決めたら、親が一貫して守ることが大切です。親の態度がぶれないことで、子どもの安定した学習習慣が身につきます。
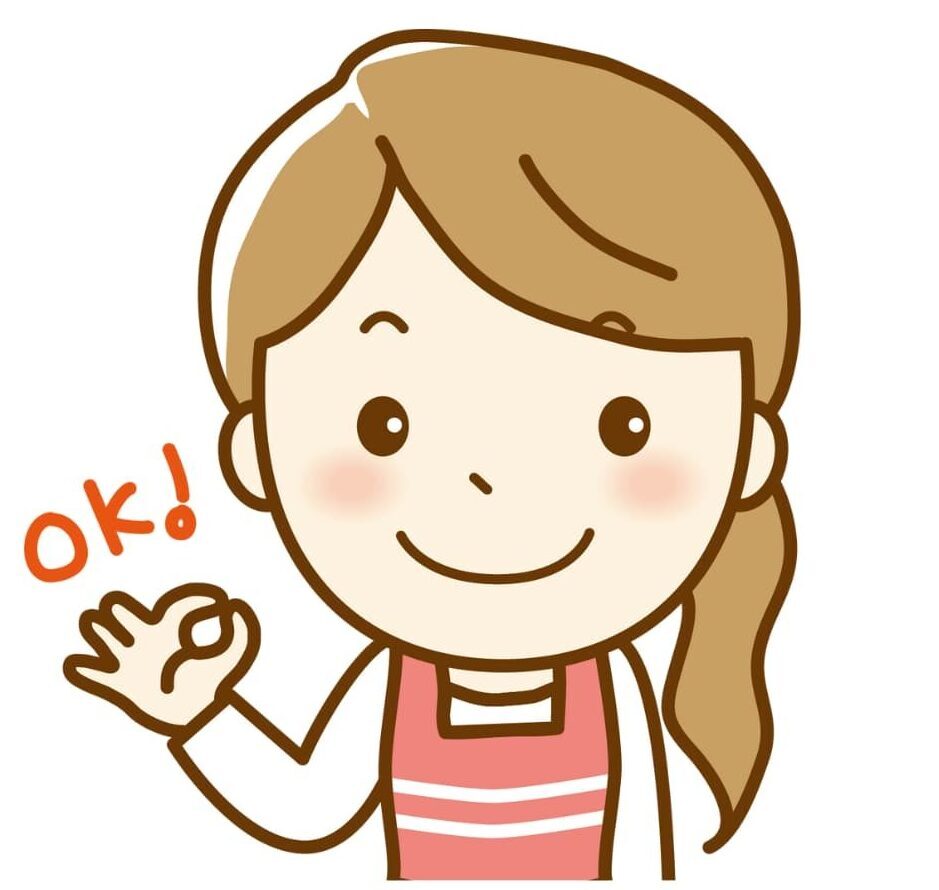
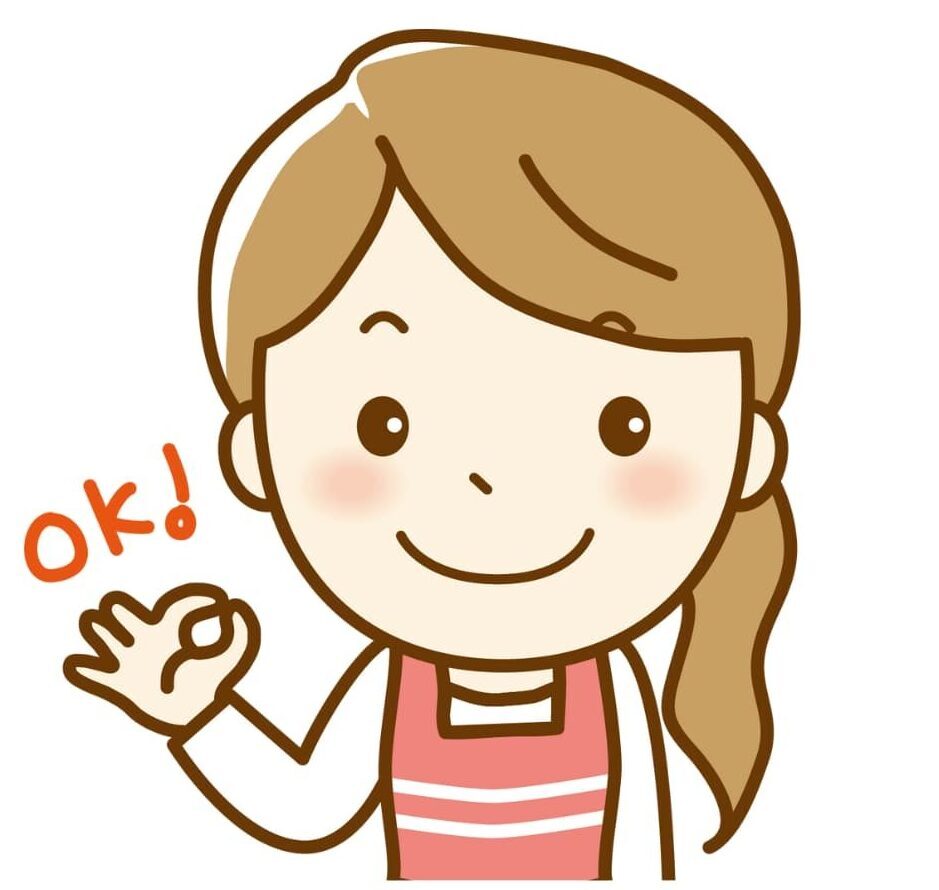
親が一貫性がないと、子供は方向性を見失います。
例えば勉強の時間を決めたら、毎日一貫して守るようにして下さい。
- Q旅行中でも勉強をしていましたか?
- A
旅行先でも、量が少なくなりましたが、お休みすることなく勉強をしていました。
悪い例


毎日勉強することにしよう!


はい…。
ある日。


今日は学校もお休みだし、「勉強はお休みにしよう!」
(本当は自分が疲れている…💦)


やった~!


< POINT>
- 親が休養日を勝手に決めるのは、子供が混乱するため、避けるべきです!
- 勉強をやらない日があると、習慣化しにくいです。
②親が言動に気をつける


1.マイナスなことは言わない
否定的な言葉や批判は、子どものやる気を削いでしまいます。失敗しても責めるのではなく、どこがうまくいかなかったのかを一緒に考え、次にどうすればよいかをアドバイスしたり一緒に考えましょう。
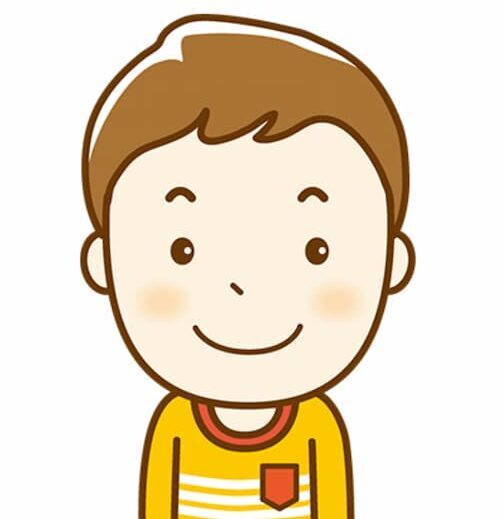
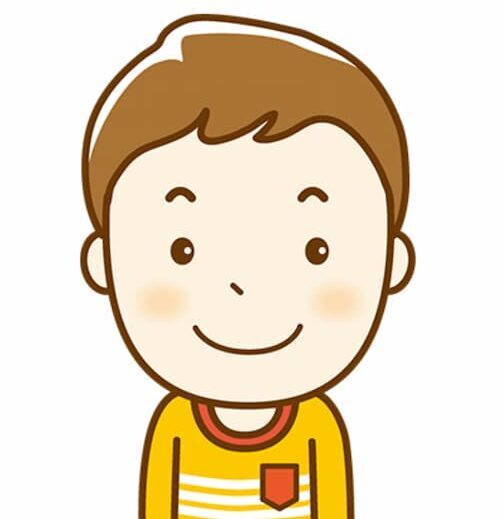
< ヒント>
いつも肯定的な言葉を掛け、失敗や苦手な部分に対しても優しくサポートするのが大切です。
「まだできないけれど、今度は頑張ろうね~ 」と接しています。
2.他人の子供と比較しない
他人と比較されると、子どもは劣等感を抱きます。比較するよりも、子どもの成長や努力を認め「前よりもよくなったね」「頑張ったね」と励ましましょう。
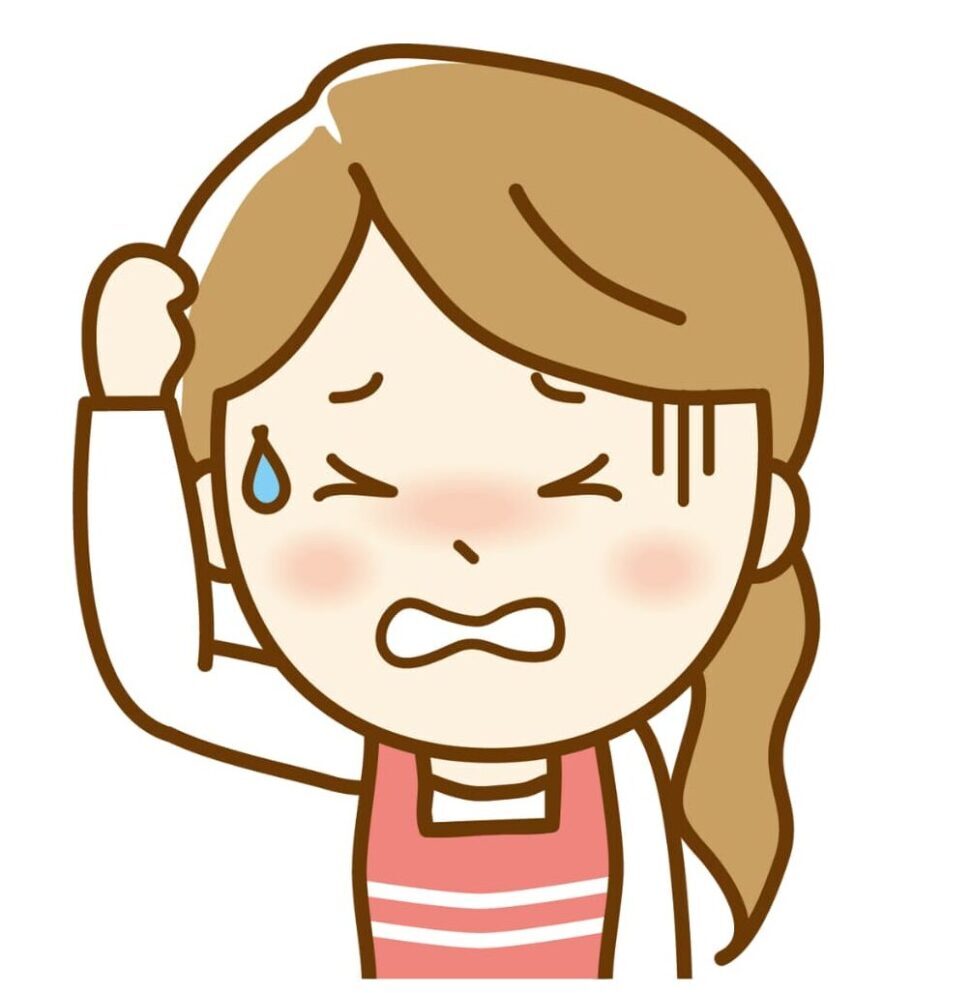
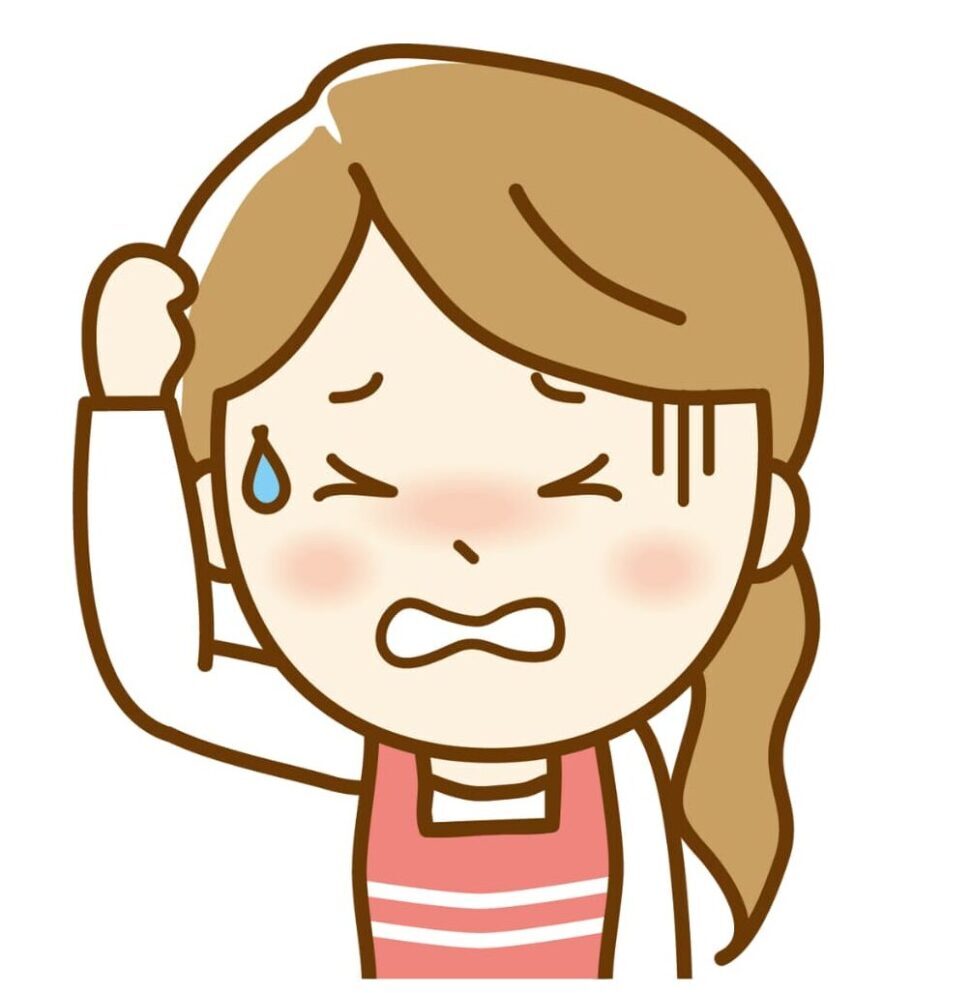
私立小学校には補欠合格で入学したので、深海魚🐟にならないか不安でした。
早生まれだったこともあり、比較しないようにしていました。
深海魚・・・学校の成績が下位層の生徒の例え
3.やる気を引き出すほめ方


具体的な努力や成果をほめることで、子どもは自信を持ち、もっと頑張ろうという気持ちが湧いてきます。
特にテスト結果をほめる際には、点数で評価しないで、毎日の積み重ねの成果と強調するのが大事です。


<具体的なほめ言葉>
| 点数が 良かった場合 | 点数が 悪かった場合 |
|---|---|
| ✔ 毎日の頑張りが実を結んでいるね! ✔ 勉強した結果がでたね! | ✔ あと1問正解なら、100点だったね。 ✔ 100点の子はいたの? |
点数で評価しないのがポイントです!
悪い例
家政婦は見た(聞いた👂)実例


なんでこの点数なの💢
こんな問題も分らないの?


分らないよ💧


明日から遊び禁止ね💢


隣の部屋から本当に聞こえて来ました。
盗み聞きになりますが…。
「やる気無くすわ💧」ってつぶやいていました。
③親も一緒に勉強する


親が学ぶ姿を見せれば、学ぶことの楽しさや重要性を自然に伝えることができます。親が本を読んだり、新しいことを調べる姿を見せることで、子どもにとって勉強が日常となりやる気を維持しやすい環境が整います。
また、子どもの勉強に一緒に向き合うことで、子どもの学習内容の理解も深まり、より適切なサポートができるようになります。
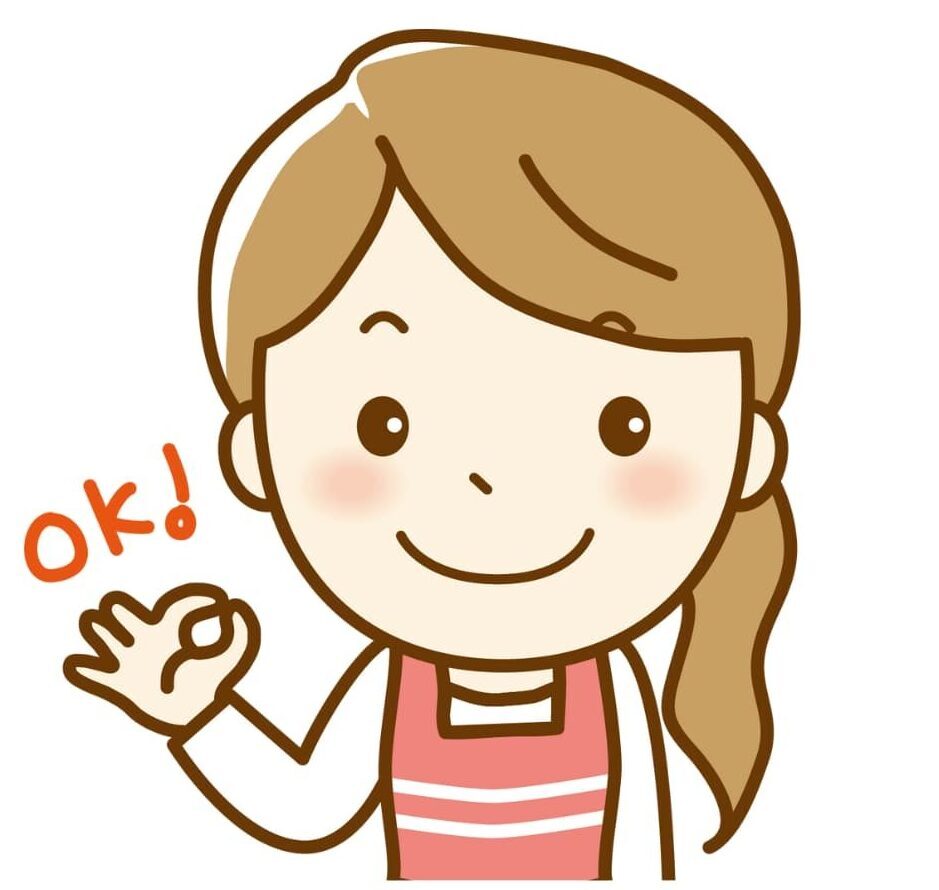
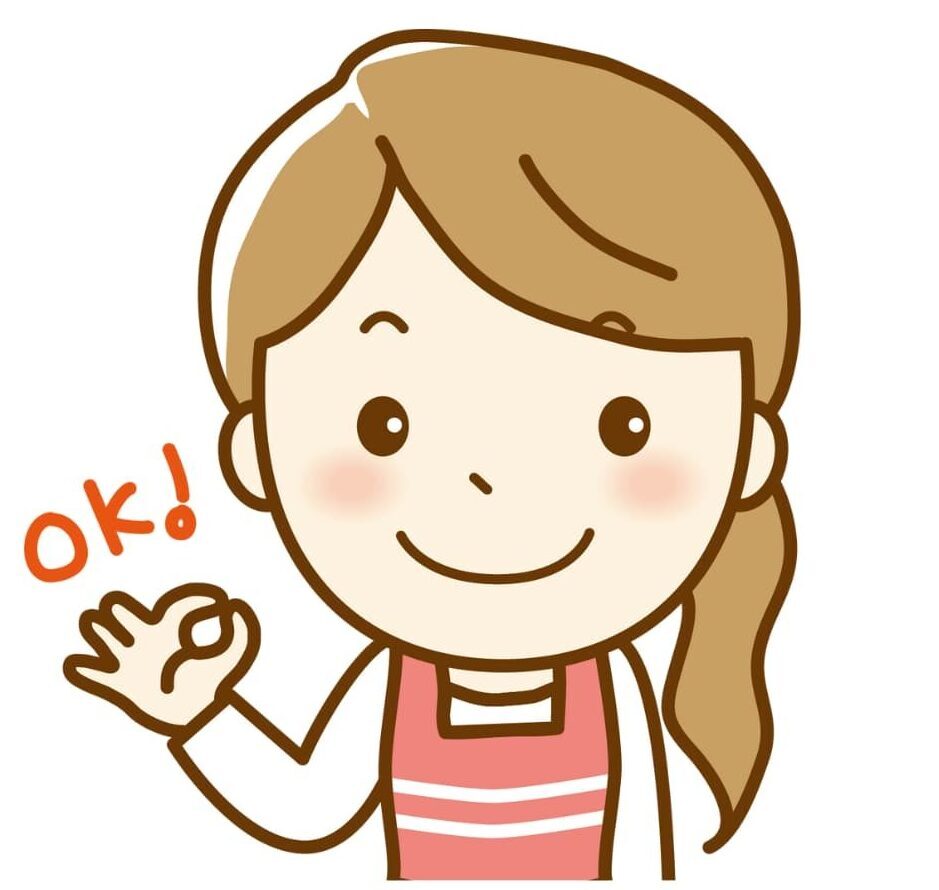
子供が勉強している時間に、読書や漢検、英語を一緒に勉強していました。
子供のやる気を引き出すほめ方とは


教員のほめ方が子どものやる気に影響を与えるか
実験内容
小学生( 2年生、4年生、6年生) に2つの場面で、9種類の異なる声掛けをし、子供の感情や意欲について調べた。
➊ 良い点数を取った時
❷ 悪い点数を取った時
9つの声掛けの方法
結果
| 意欲 | 声掛けの方法 |
|---|---|
| 促進 させた | ➊ 努力を認めた言葉 ❺ 努力へ期待を示した言葉 |
| 低下 させた | ❸運 ❻問題の困難度を理由にした言葉 |
ほめることの欠点
結論


調査結果
子供のやる気を引き出すためには、努力を認める周りの人間の存在が重要です。
また子供が期待されていると感じると、努力を惜しまなくなります。
まとめ


子供のやる気を引き出すには、親や周りの存在や関わり方が重要で接し方でも変わるのが分かりました。
勉強を継続するには、子供がストレスなく勉強に取り組める環境を整えることが大切です。
まずは、モチベーションアップの作戦の声掛けを試してください。期待されているのと感じるとやる気になるというのだから、誰でも無料でできますね。
小さな成功をほめることで、子どもは自信を持ち、継続して努力することができます。ぜひ実践してみてください。
コメント