
 あや
あやこのような 疑問はありませんか?
こどもの知的好奇心を伸ばすメリットとコツは?
知的好奇心を刺激するあそびも知りたい!
この記事では、子どもの知的好奇心を伸ばすメリットやコツ、知的好奇心を高めるあそびを紹介します。



子どもが小さいころ、何が正解か分かりませんでした。
実践して良かったことをお伝えします。
記事の後半では、大学時点での学力の差を生んだ子育て方法のデータも解説しています。
ぜひ参考にしてください。
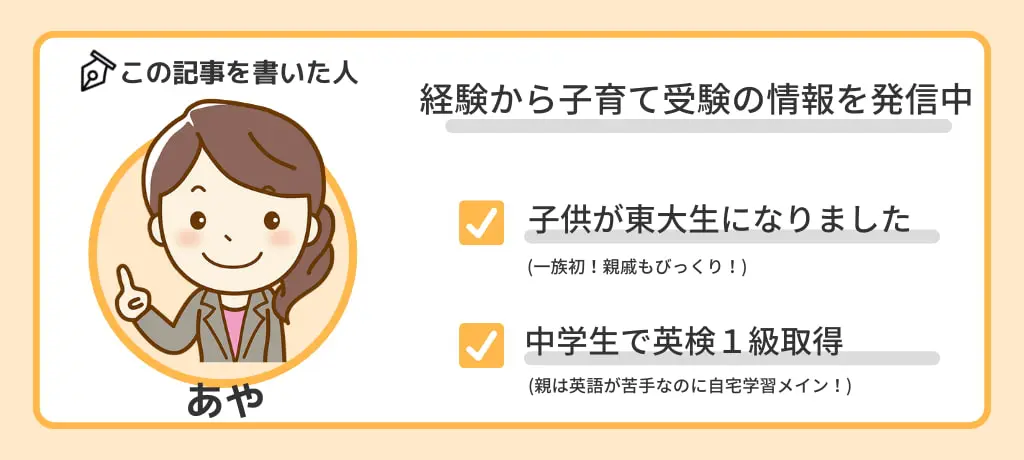
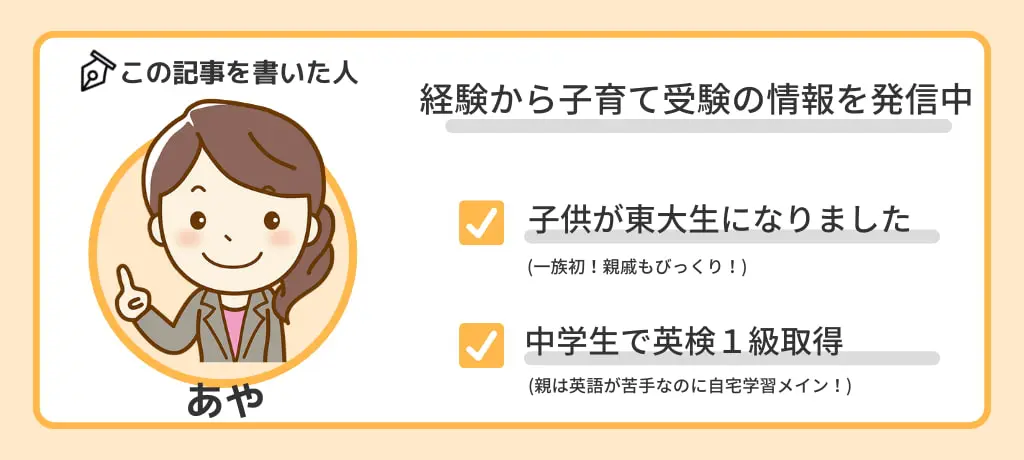
知的好奇心を伸ばすメリットとは


知的好奇心とは、新しい知識や情報、経験を求める強い意欲や関心を持つ状態のことです。
子供ならだれでも、「これって何だろう?」「これを知りたい」って感じる自然の気持ちです。



子供の知的好奇心を伸ばせば、多くのメリットがありますので紹介します。
- 探究心が強くなる
- 意欲的に学習に取組める
- 集中力がつく
- チャレンジ精神が身に付く
①探究心が強くなる
知的好奇心が高い子供は、知らないことや未知のことでも積極的に知ろうとします。
分からないことがあったら、質問を投げかけ、情報を収集し、理解を深めていきます。
子供が「どうして?」という気持ちを解決すると、「分かった!」というプロセスに喜びを感じようになり、探究心が強くなります。
②意欲的に学習に取組める
知的好奇心があると、知らないことを積極的に学びたい欲求を持ちます。子供は知らないことを自ら学び、疑問を解決する楽しさを感じながら成長していきます。
「やりなさい」と押しつけられた学習ではなく、自分の興味から学ぶため、さまざまなことを吸収していきます。
「分かった!」という気持ちから「もっと知りたい!」と変化し、意欲的に学習に取り組むようになります。
③集中力がつく



子供が遊びに夢中になって声をかけても気づかない、そんな経験はありませんか?
知的好奇心が高い子どもは、自分の興味を示したことに没頭する傾向があります。好きなことを調べたり覚えたりする過程で脳が刺激され、集中力が高まっていきます。
例えば、好きな昆虫の種類をたくさん知っている子供や、電車の型式まで言える子供などいるかもしれませんね。
知的好奇心が育まれている状態では、子供は集中力はもちろん、記憶力や観察力も鍛えられます。



どの子供も、親が気づかないだけで、能力を秘めているので見つけてあげましょう。
④チャレンジ精神が身に付く
知的好奇心は創造的思考を促進します。今までの常識や既成概念にとらわれず、新しい視点で考えようとすることで、問題解決に柔軟に対応したり、未知の発見にチャレンジできる精神力も身に付きます。
子供の「できない」や「やりたくない」という気持ちが、「やってみようかな」と挑戦する気持ちに変わり、チャレンジ精神を育むことができます。



子供は自分の好きなことをしているだけで、たくさんのメリットがあります。
知的好奇心を高めるコツ5選!



知的好奇心を高める5つのコツを紹介します。
- 子供の疑問を解決する
- 子供の興味を見逃さない
- 子供の興味を楽しむ
- 子供の興味を維持する環境作り
- 図鑑・地図・辞書・新聞などをリビングに置く
①子供の疑問を解決する


子供が質問してきたときは、知的好奇心を伸ばすチャンスです。質問された時点で時間がなくても、すぐに対応するのが大事です。



手が離せない時は、終わる時間を教えてあとで丁寧に答えてね。
NGワード
- 何度も同じこと聞かないで
- 面倒くさいな
- 忙しいからあとにして
- そんなことどうだっていいでしょ
親がすぐに答えが分かっている内容でも、一緒に調べ考えるプロセスが大事です。
「何をみたら分かるかな?」と調べ方のヒントを出してみるとよいでしょう。
自ら調べて分った事は忘れにくく、「また調べてみよう」という動機付けにもなります。
②子供の興味を見逃さない
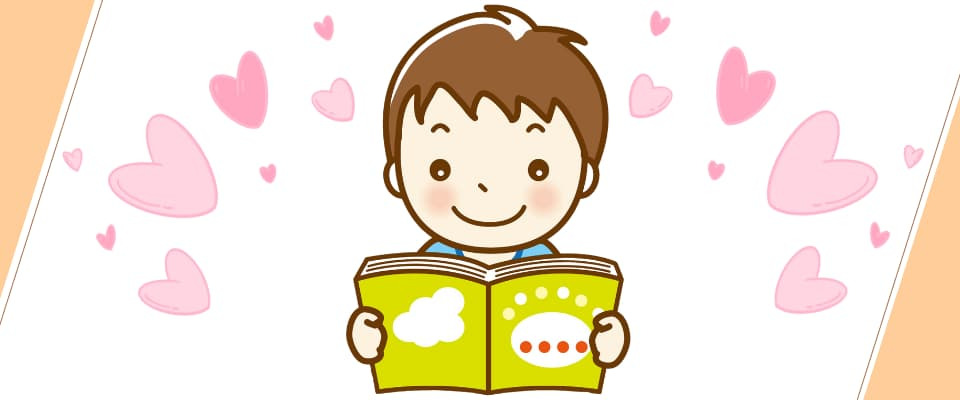
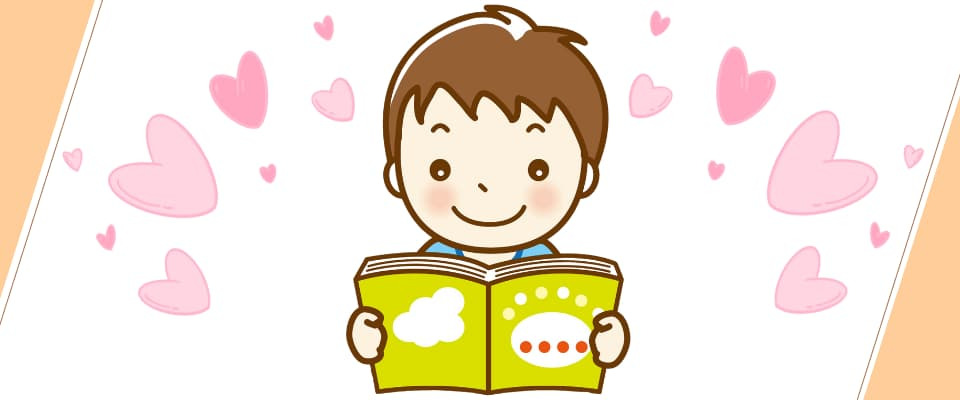
子供が質問をしてこないからといって、うちの子は何も興味をもっていないと考えるのはもったいないです。



お子さんにこんな変化はありませんか?
発見のサイン
- いつもより興味を示している
- 楽しそう
- 何度も同じ本を読んでいる
- 繰り返し質問してくる
親がささいな変化に目を向けて、子供の好きに気づいてください。
例えば、アニメが好きそうならキャラ図鑑を買って読んで見る。電車に興味を持っていると感じたら、電車を見に行ってみる。



好きかも?と感じたら、なんでも試してみるのも大事です。
③子供の興味を楽しむ


子供の興味を見つけたら、ラッキーな出来事の始まりです。



興味のある関連している場所に一緒に出かけて、関心をさらに深めましょう。
具体例
- 飛行機に関心をもったら、飛行機の工場見学に行く
- 電車が好きなら、鉄道博物館に行ってみる
- 恐竜に興味があるなら、化石発掘に連れて行く
- 魚や昆虫が好きなら、家で飼育して観察する
- 虫が好きなら、図鑑をもって外出する
子供の「分かった!」という気持ちが満たされると、さらに「また知りたい!」という効果を生み出します。
NG行動
- 親の趣味を押しつける
- 子供の趣味に制限をかける
- サポートをめんどくさがる



子どもが興味を持ったら、芽をつぶさないために注意しましょう。
我が家の知的好奇心を刺激した例
電車好きな息子と一緒に、本の中でしか見たことのない電車を見に行ったり、イベントなどにも参加しました。
ドクターイエローに出会った時は、鳥肌が立つほどの興奮を味わいました。
また、現在廃線となった電車に乗ったのも良い思い出です。



どこに行くのかを事前に一緒に調べて確認するのが大事!
④子供の興味を維持する環境作り


子供の知的好奇心を育てるために、興味をもっているものや関連するものを買ってあげましょう。
日常的に好きなものに囲まれることで「もっと知りたい」という気持ちがさらに刺激され、良い効果をもたらします。
電車好きにおすすめ
- 電車が好きなら、プラレールを揃えて遊ぶ
- ミニカーに興味を示したら、ミニカーと本を買ってみる
- 食べるのが好きなら、料理やお菓子作りに挑戦する
- 星や宇宙に憧れたら、星座盤や望遠鏡で天体観測に挑戦してみる
子どもが好きなことをしているだけで、自然と覚え、知識豊富に育ちます。



鉄は熱いうちに打て!子供の興味が変わらないうちに行動してね。
知的好奇心を伸ばすために購入したもの
我が家では、電車好きの息子のために下記を購入しました。
電車好きにおすすめ
- 地図帳(本)
- 日本地図の大きいポスター
- 電車の路線図のポスター
- 地球儀



電車や地図のおかげで、地理も得意になったよ👍
⑤図鑑・地図・辞書・新聞などをリビングに置く


図鑑・地図・辞書・新聞などは、子供の知的好奇心を伸ばす必須アイテムです。
分からない時にすぐに解決できる環境を整えるために、リビングに置くのがポイントです。
子供が分かるように目立つ場所に置くことで、自然に調べる機会も増えます。
もし、一人で調べて答えを出せることができたら大いに褒めてあげれば効果も倍増です。
子供の知的好奇心を高めるあそび





知的好奇心が高まる手軽にできるあそびを紹介します。
- アウトドアの活動
- ボードゲームやカードゲーム
- 親も新しいことにトライする
- 読書をする
①アウトドアの活動
普段の公園でも、よく観察すると季節によって違う花が咲いていたり、虫の音が聞こえたりとさまざまな発見が見つかります。
どんな変化があるのか五感を刺激し、気づかせれば、興味をもって観察するきっかけとなり、好奇心を伸ばせます。



夏休みなどにキャンプに行くのは特におすすめです。
火をおこして炊いたご飯や美味しいお肉を食べたりしながら、リラックスできますし、自然の中で空や風、植物、昆虫などの多くの発見があり、普段の生活では味わえない体験ができます。
②ボードゲームやカードゲーム
家族でのあそびタイムにボードゲームやカードゲームを取り入れると、ゲームを通してルールを覚え知識を増やしていけます。
また、ゲームでの勝敗にこだわることで勝つために考えて遊ぶチャレンジ精神も育まれます。
ゲームを楽しむポイントは親も本気で勝負すること。



子供に手加減をして負けていては駄目ですよ。



将棋の藤井聡太さんは、5歳に時におばあさんに「KUMONのスタディ将棋」のボードゲームをもらったのがきっかけとのことです。



上の画像 のカードゲームは、ぼくが使っていたものです。
四字熟語と百人一首は、家族でよくやりました。
③親も新しいことにトライする
子供の様子をみて変化がなくて、がっかりすることもあるかもしれません。
でも、大丈夫です。普段は仕事で忙しくても、休みの日に今まで行ったことのない場所やはじめての体験を一緒に楽しむと可能性が広がります。



親が楽しそうに取り組んでいれば、子供も自然と興味関心を持つきっかけになります。
④読書をする
子供が本を読むことはもちろん大切ですが、違うジャンルに興味を広げてみるのも良いでしょう。
興味がないことでも一緒に読んであげることで、子供が新しい発見をし、ワクワク感じるきっかけになります。



どんなことに興味を持つのかは分からないので、本で気軽に試してみてね。
知的好奇心を育てる幼児期の親の関わり方とは


「学力格差は幼児期から始まるのか」という研究を参照しています。(参照元:お茶の水大学)
調査内容
2000組の保護者に、子どもが小さい頃「何に配慮して子育てしたか」を回答してもらい、大学進学時の成績と関係があるのかを調査しました。
成績
| 項目 | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| 偏差値68以上の 大学突破経験者 | 35.8 | 26.3 | 24.1 |
| 未経験者 | 23.1 | 15.3 | 12.7 |
調査結果
以下の3点に配慮し子育てした子供の成績がいい結果となりました。
- 思いっきり遊ばせる
- 遊びの時間を子供と過ごす
- 子供の好きなことに取り組む
また、受験偏差値68以上の難関大学を卒業した子をもつ親は、以下のように回答したのが多かった。



子どもと一緒に遊び、子どもの趣味や好きなことに集中して取り組ませました。
知的好奇心が高かった同級生たち


高校受験をし進学した学校で出会った同級生たちは、多様な興味を持つ子が多かったです。
アイドル、楽器、ゲーム、投資、ディズニー、天文など、さまざまなジャンルに詳しい同級生たちと出会い、刺激を受けました。



同級生たちとの出会いで感じたのは、それぞれの家庭でも子供の好きな事をみつけて伸ばしていったのではないかと、推測しています。
まとめ


子供の知的好奇心を伸ばすためには、小さい頃の疑問にしっかり向き合ってあげるのが大切です。
子どもの好きなことを見つけたり、付き合うのは簡単ではありません。
けれど、幼少期に何かに没頭する経験があるかが、自主性や自発性を形成する上で重要な要因であると分かりました。
好奇心を大事に育み、成長をサポートすることで、子供の好奇心を刺激し、子供の学ぶ力が育ちます。
親にとっても、子どもにとっても、将来の最高の財産ですね。
付き合うのが大変な時は、水やりをやっているつもりで楽しんで取り組んでください。


コメント